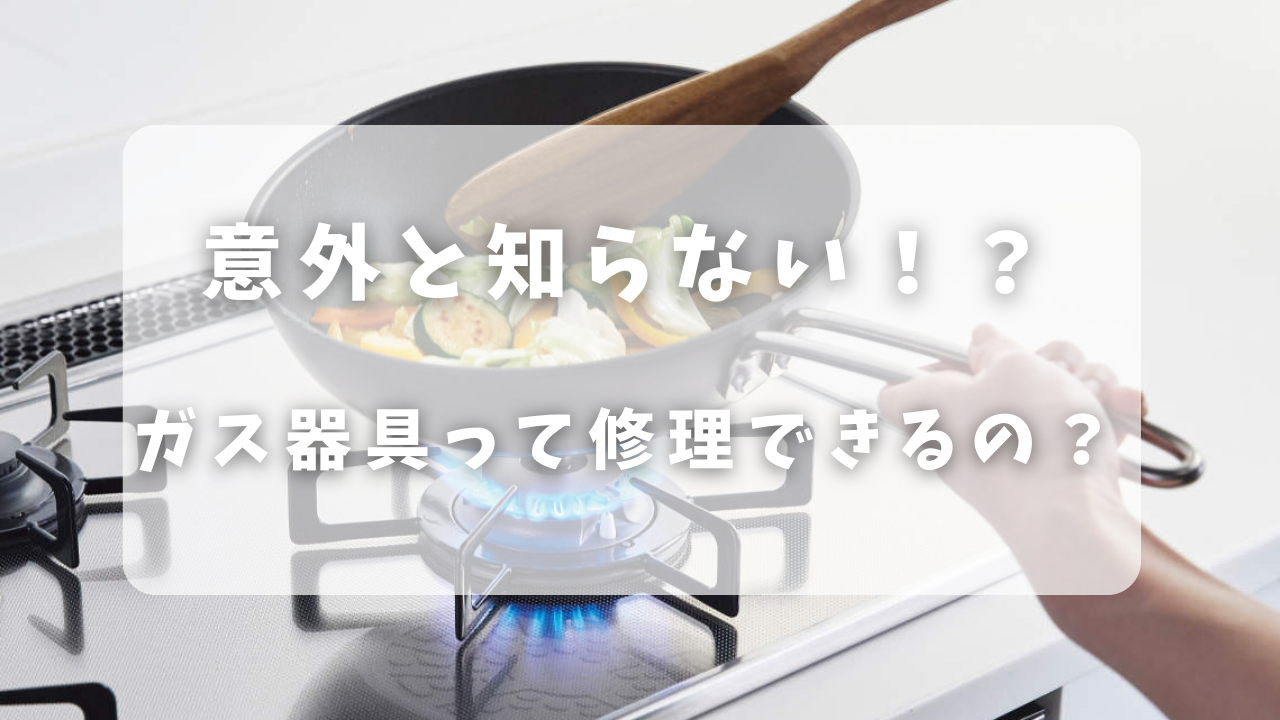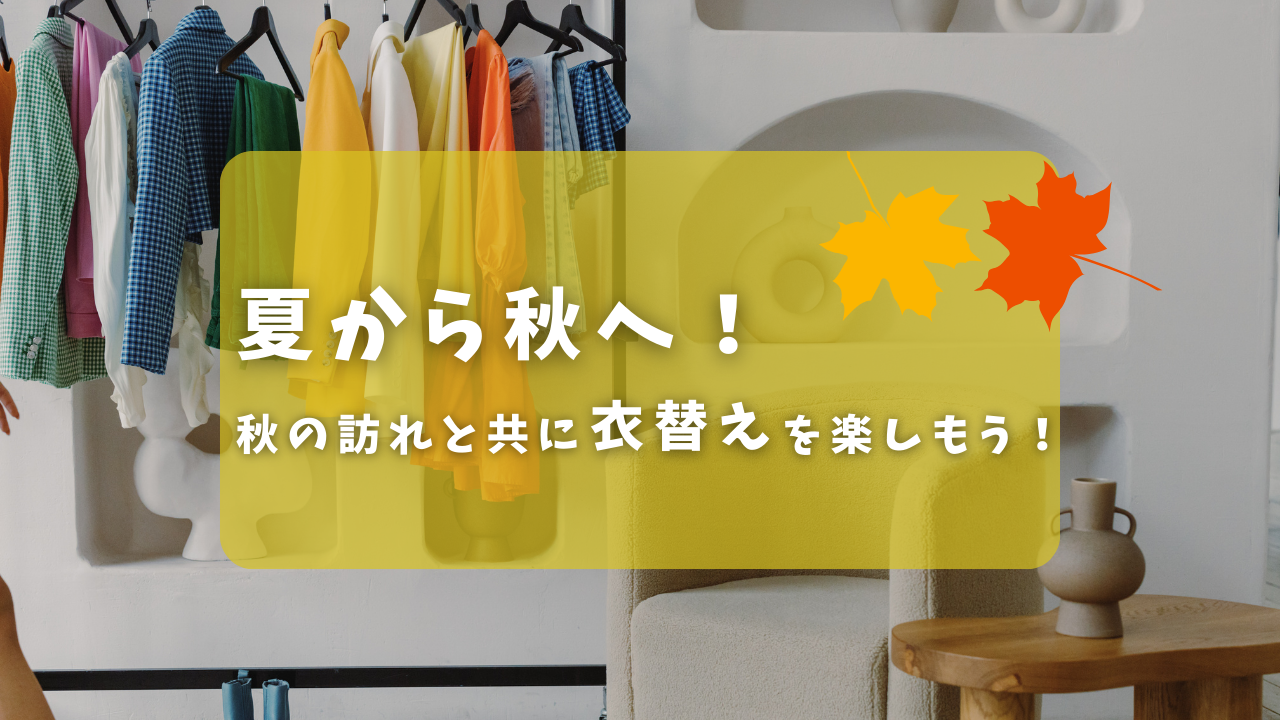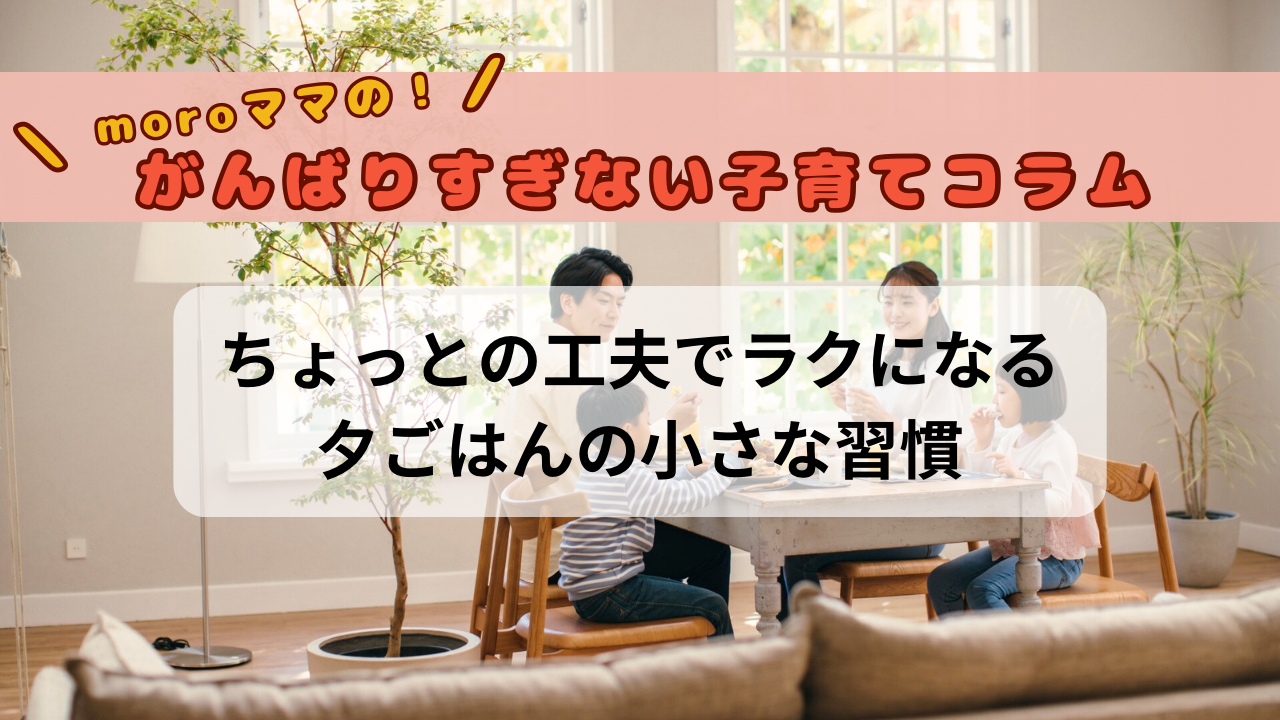
ちょっとの工夫でラクになる 夕ごはんの小さな習慣
夕ごはんの時間、みなさんのおうちではどんな光景が広がっていますか?
我が家は、こどもたちの「お腹すいた!」の声が響き、バタバタと夕ごはんの支度が始まります。食卓ではこどもの様子を見守りながらあれこれと話が弾み、慌ただしく時間が過ぎていきます。
家族揃って食卓を囲む夕ごはんの時間は、みんながちょっと一息つける大切な時間でもあるため、楽しい時間にしたいものです。毎日のことだからこそ、負担を減らしたいですよね。
今回は、「ちょっとの工夫でラクになる、夕ごはんの小さな習慣」を紹介します。
夕ごはんの小さな習慣

夕ごはんの時間を、笑顔でゆったりと過ごすために取り入れた、3つの小さな習慣をお伝えします。
ちょっとした工夫で、親もこどもも夕ごはんの時間をもっと気持ちよく過ごせるようになりました。
「いただきます」「ごちそうさま」は当番制
曜日ごとに「いただきます」「ごちそうさま」を言う当番を決めています。親が毎回声をかけなくてもこどもたちが「今日は自分の番だ」と意識するので、食事の前に自ら席に着く習慣がつき、親の声かけが減りました。
さらに「今日は◯曜日だからお母さんが当番だね」と自然に曜日感覚が身についていましたよ。

今日の出来事を全員で共有する
食事をしながら、家族全員が順番にその日の出来事を話す時間を作っています。一日を振り返り、こどもたちが自分の気持ちや出来事を伝える習慣が身につくことで、コミュニケーション力や自己表現力の向上にもつながります。
また、些細な出来事でも家族で共有することで、親も子もお互いの状況を把握し、思いやりの気持ちや困った時はサポートする気持ちが自然と芽生えるようになりました。

「お助けカード」でこどもが自分のごはんを用意
食事を作る余裕がないときに「お助けカード」というものを使って、こどもたちに自分で食事の準備をしてもらっています。火を使わなくても食べられるような、バナナやヨーグルト、納豆やコーンフレーク、パンなどを自分で選んで準備します。親の負担を減らすだけでなく、自分で用意することで達成感を得られ、次第に自発的に手伝おうとする姿勢も見られるようになりました。

まとめ

夕ごはんの準備から片付けまで、こどもの様子を見ながらたくさんのことをこなしていかなければいけないため、余裕がなくなる日もあります。しかし、家族そろって食卓を囲む時間は、できればみんなが笑顔で過ごしたいですよね。我が家は、小さな工夫を積み重ねて習慣化していくことで、こどもは自立し、親も心にゆとりが生まれましたよ。
みなさんも「頑張りすぎない」ことを意識しながら、夕ごはんの小さな習慣を取り入れてみてください。


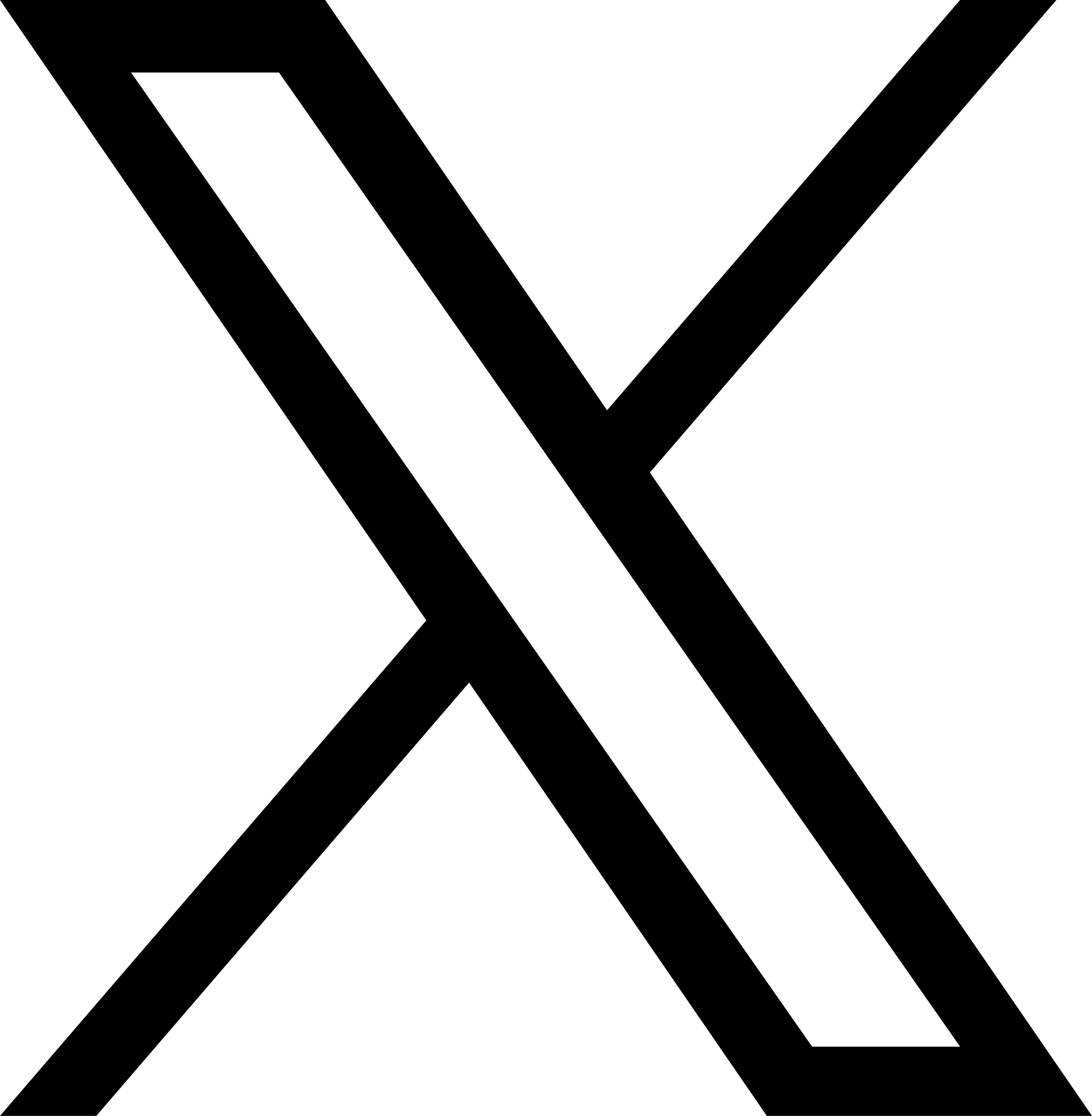

からの-1-2.png)